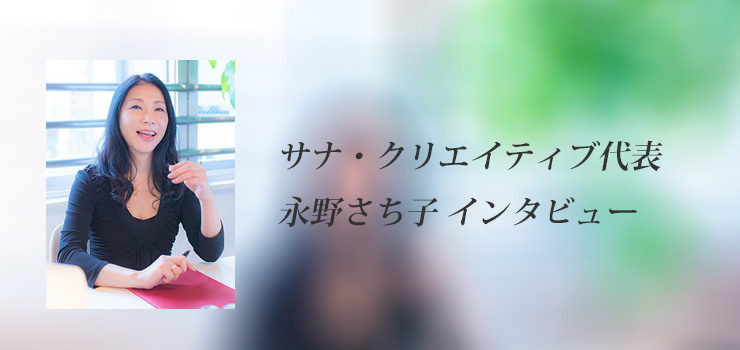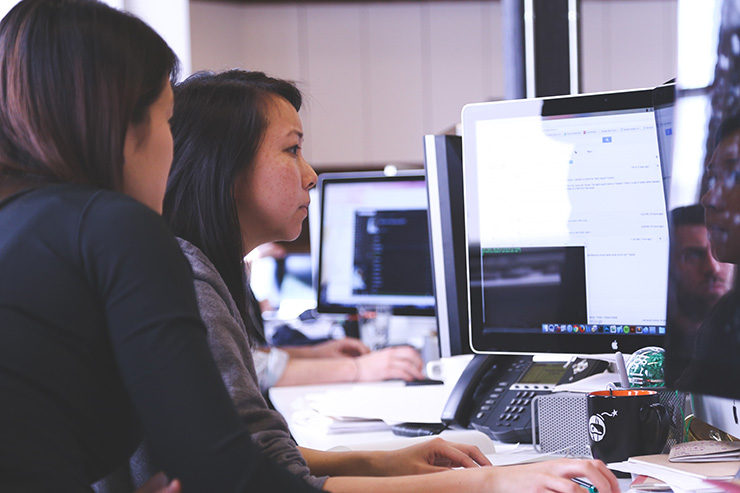そもそも「セルフブランディング」とは?
「セルフブランディング」とは、自己を意味する「セルフ」と顧客の共感や信頼を高めるマーケティング戦略として知られる「ブランディング」を合わせた複合語です。ブランディングは商品を販売する際に使われますが、セルフブランディングは自分自身を商品として、その価値を高めることを意味します。また、生き方・働き方・信念を軸とする「インナーブランディング」と、ロゴ・デザイン・容姿といった「アウターブランディングに分けられます。
多くの方は芸能人や政治家、起業家(フリーランス)にのみ必要なスキルと認識していますが、平成も終わりに近づいた現在、老若男女問わずどんな方でもセルフブランディング力は必要不可欠なものになっています。
ではなぜ近年、より多くの人にセルフブランディング力が求められるようになったのでしょうか?
セルフブランディングがカギになる。時代の変化に合わせた働き方。
ここ10年間の間にインターネットは著しく発展し、それに伴いSNSの利用者も急激に増加しました。誰もが簡単に情報を発信したり、仕入れたりできるような時代になった一方で、我々はその情報が正しいものか誤ったものかを見極めなければなりません。そこで重要になってくるのは、「誰から」情報を受け取るかということ。私たちは自ら果たすべき役割や、生み出せる価値を発信することで、共感や信頼を得ることを重要視するようになったのです。
この10年の間にインターネットが中心となった社会に大きく変化したように、10年後の未来を誰も想像できません。今当たり前と言われていることも、10年後にはそうでなくなっているかもしれません。
アメリカでは企業や組織に所属せずに働く「フリーエージェント」という言葉があり、すでに個が力を持った働き方は日本よりも進んでいます。アメリカにおけるフリーエージェントの数は、人口の3分の1にも及んでおり、今後日本でもそのような人が増えていくと考えられています。
ではこのまま不安と共に変わりゆく時代を生きていかなければならないのでしょうか?
時代が変化しているのであれば私たちの在り方や働き方も同様に変化してかなければなりません。
何が正しいか定義づけされていない世の中だからこそ、企業や組織に依存せずに個人の能力を生かした働き方をしていく必要があります。一方で企業としては、個人の能力を最大限発揮できるような組織づくりが企業の成長に繋がっていくのではないでしょうか。
そこで鍵となるのが、セルフブランディングです。
冒頭でも述べたように、セルフブランディングは芸能人や政治家、起業家(フリーランス)に限られたスキルではありません。就職活動をする際にも、自分にしかできない価値をアピールすることは大きなアドバンテージになりますし、もっと身近な例としては、恋愛や友人関係においても同様のことが例えられます。これら全てに共通して言えることは、「特定の人」に求められる存在になること。芸能人であればファン、政治家であれば有権者、起業家であれば顧客、恋愛であれば恋人など全てにおいて特定の人に求められています。このことこそが、AIの発達など今後何が起こるかわからない時代を生きていくにあたってあなた自身の不変の価値になるのです。
具体的な実践方法
では実際にセルフブランディングを行うにあたり、具体的な核の決め方ついて説明します。
- 核を決める
自分の強みは案外普段当たり前にやっていることが多く、自分のことを客観視することは難しいので友人や家族に自分の強みを聞くのも一つの方法です。自分の強みや幼少期に得意だったこと、今までの成功体験をもとに考える自己分析と並行して他己分析を行うことでより自分の軸となるものが形成されます。また自分の強みは、周りや社会にどんな影響を与えることができるのかも併せて考えるとより具体的に「自分」について説明できるようになります。 - 発信する
セルフブランディングという言葉通り、自分の核となる考えは誰も拡散してくれるわけではなく自ら発信して周りの人からの共感や信頼を獲得しなければなりません。どのSNSやブログを使って、どうやって発信するかを決めるのはアウトブランディングにあたります。せっかく、核となるものが立派なものでもそれがうまく伝わらなければもったいないので、伝え方にも試行錯誤が必要です。
各々が個人の強みを把握した上で、その能力をどう育て企業の成長に繋げていくのか。それを考えるためにはまず個人がセルフブランディングを行う必要があるということです。
最後に
職業や働き方を問わず、個人として何ができるのか、どんな価値を生み出せるのかを自分自身で把握することさらにはそれを発信することは今後とても重要視されていきます。企業に勤めている人も、個人で活動している人も1度だけの人生だからこそどう生きていきたいのか、どんなことで世の中に貢献したいのかを考えてみてはいかがでしょうか。
(文責:長谷川)